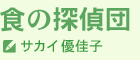干し芋を題材にした時は、「茶色っぽいけれど、ところどころ薄緑色に見える。手でさわるとベタベタ。口の中で歯にねっとりとくっつく。よく噛んでいると甘みがじわっとひろがる。甘い香り。ひなたの香り。まわりに白い粉がついている」といったように、小学校低学年の子たちからもさまざまな表現がでてきて、いつもホワイトボードに書ききれないほど。表現力がないといわれる最近の子供たちですが、ゆっくり時間をとり、機会を与えれば、こんなに多彩な表現がでてくるものか、とこちらが驚かされます。
ある時、サンドイッチを作って食べて、その「観察結果」を発表してもらっていた時、小学校4年生の男の子が「そよ風がふく草原でのピクニック」と発言しました。お手伝いに入ってくれていたお母さんたちも一瞬「?」と首をかしげたのですが、その後、皆笑顔になりました。きっとその子はサンドイッチをもって家族や友達と「そよ風がふく草原でのピクニック」を楽しんだ思い出をもっているのでしょう。その子の素直さ、家族とのかかわりまでが透けてみえる表現で、こちらまで幸せな気分になりました。こんなふうな食の体験を積み重ねて育っていけば、彼は毎日小さな幸せを見つけていけるに違いありません。
大人のプログラムの場合、素直な表現がでてくるまでには子供より時間がかかります。「あまり平凡なことをいいたくない」とか、「ちょっといいところ見せたい」などといった意識がどうしても働いてしまうのかもしれません。あるいは、「こう発言しておけば、とりあえず間違いではない」といった思いが先行してしまうのかもしれません。アンチョビを試食した時にも、「パスタとあわせて食べたいと思いました」といったことがまず初めにでてきてしまうのです。自分でその場で味わっての観察というよりは、今まで得た知識に基づいた回答が多いのが残念です。