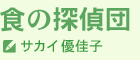言葉の感覚が時代とともに変化するのは自然です。ただ、今の私たちの生活の中では、物事や気持ちをきちんと表現してみようという努力をすることが少なくなっているように思えます。フランス味覚研究所のジャック・ピュセ氏は、差が認識されなければその差を表現する言葉も必要なくなってしまう、として、じっくりと観察し、その差を味わいわけることの大切さを指摘しています。きちんと表現しわけようという努力をせずにずっと過ごしてしまうと、差を味わいわけることに意味を見出すことすらできなくなるかもしれない、といったら言い過ぎでしょうか。
私たちの周りを見ると、「いつ行っても、どこの店で食べても同じ味」ということが安心なのか、ファミリーレストランやファーストフードなどの大チェーン店が林立してきています。ここでいう「安心感」は、お袋の味、家庭の味が与えるそれとは異質のものです。こうした店の多くは、工場で集中調理して輸送し、店では温め盛り付けるだけというシステムで動いており、各店舗においては、調理技術は基本的に不要です。そして大量に同じ規格の食材を必要とするために、多くの場合海外からの輸入食材が使われ、更には調理済み食品を輸入するといったこともあたりまえになっています。
一方で、テレビなどでおいしい店と取り上げられると、自分自身の感覚に素直になれずに、おいしいと思えなくてもおいしいと無理に感じてしまう、その店で食べるという行為自体が目的になってしまう、そんな状況も見えてきます。作り手や店によって違う雰囲気や味を楽しむというよりは、情報としておさえておかなくては、といった思いが優先している場合も少なくないように見えます。