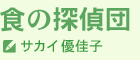あるインド人から「手で食べないということは、食べ物を味わう重要な感覚のひとつを放棄するに等しい」と言われたことがあります。日本でも手で食べるのが普通のものはいくつかあります。おにぎり、サンドイッチ、寿司、枝豆、空豆…。おにぎりを箸で食べたらやはり味が違うように感じるのではないか、とその時思いました。人の手で握られたおにぎりのふんわり感と同時に感じる米の飯の重み。これがあるから永遠の定番としておにぎりは人気があるのかもしれません。
フランス語には香りを表す言葉が他の国の言語に比べて多いといいます。日本語は、触感を表す言葉が多いのが特徴との研究結果を先日知りました。意識していなくても、私たちは触感の差でおいしいと感じたり、そうでもないと感じたりすることがきっとあるはずです。
中学生の頃、一時魚をおろすのに夢中になった時期があります。ある時ニジマスに何気なく触ったところ、ヌルっという川魚独特の手触りに思わず後ずさりしたのを今でも覚えています。ある友人は子どもの頃にぬかみそをかきまわす感触がたまらなく好きだったと言います。うどんを家でうつ家庭では、うどんを踏む足の裏の感触に思い出があるかもしれません。
名画「泥の河」の中で、貧しい少女が米びつの中に手を入れている温さが安心できて好きと語る場面が今でも印象に残っています。この映画を見たのはもう10年以上前ですが、米を計るたびに思い出し、私もその感触を意識するようになりました。茶碗やお椀の重さ、口あたりの薄さ厚さ、箸の感触、など使いやすいお気に入りの食器には、見た目の色や形以外に触感が大きく影響しています。
ビールやカプチーノを飲む時に上唇に着く泡もおいしさのうち。粉から餃子の皮を作ったり、パンを焼いたりの時には、手で触った感じでこね終わりを決めます。コリコリする軟骨の旨さをおいしいと感じるのか、気持ち悪いと思うのか。舌で感じる味覚以外の要素として触感は私たちの感じ方に大きく影響しています。