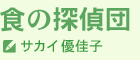◆エピソード1(変幻自在レシピ)
大人版では、家庭ですぐに活かせるように、と、「変幻自在レシピ」というプログラムを入れています。ある時は酸味、ある時は甘味に、とポイントを決め、その味をだす食材を変えてみる、あるいは、同じ味付けであっても、そこに加える食材によって、見た目や香り、味わいが変わることを、実際にそれぞれの料理を作り分け、試食してもらい、体感してもらいます。自分が持っている料理の本や、テレビや新聞などで紹介されているレシピから、どうアレンジしていけばいいのかの、ちょっとした頭の体操です。このプログラムを考えついたのは、小学校や幼稚園を通じておつきあいのあるお母さんたちが一様に「献立がマンネリ」と口にすることからでした。
某マーケティング会社が行った調査では、「レシピどおりに作る料理こそ、きちんと作られた料理」といったマニュアル世代ならではの回答が多く見られたと報告されています。となれば、レシピどおりに作ったのにうまくいかなかったら、自分は料理が下手と自分をせめてしまうことになり、そしてそれが続けば「料理が嫌い」となってしまっても不思議ではありません。もちろん多少の基礎は必要ながらも、料理はもっと自由に楽しめるはずのもの、という思いが私にはあります。
友人から、「よくそんなにレシピを考え付くわね」と言われますが、気が付けばいつも新しいレシピを考えているような生活をしていると、レシピはいかに応用し、展開していくかで、いくらでも生み出せると断言できます。要は食べることに興味や関心があって、先入観をできるだけ捨てて食材と向かい合うことができれば、そんなに難しいことではないのです。
今回も酸味をきかせた煮込み料理を作っていた時のこと、4種類の料理を食べ比べながら、「これには他にどんな野菜を入れたらいいでしょうか?」と質問してきた40代くらいの女性がいました。私がいくつか思い付く野菜の名前を口にすると、質問した本人が、「色がもう少しあるときれいだし、パプリカなんか入れるといいかもしれませんね」と発言したのです。そうそうその調子!我が意をえたり、とうれしくなった瞬間でした。
◆エピソード2(味のふるさと)
大人版に取り入れたいと思いながらも、時間がかかるために中々実現できないプログラムのひとつに「味のふるさとを探る」があります。自分たちにとっての懐かしい味、思い出の味を書き出してもらい、その情景をできるだけていねいに表現してもらうのです。とても興味深いものですし、自分の味の原点を知るためにも是非ご自分でやってみて、できたらメールで教えていただけたら嬉しいです。
私たちの印象に残っている味の多くは、その味わいだけではなくて、香りや見た目、さらには一緒に食べた人、情景、明るさなどまでがくっついて思い出されます。ある人にとっては放課後に帰宅途中の公園で紙芝居を見ながら食べたソースせんべいの薄っぺらい味。仲良しだった友達の顔まではっきりうかんでくるといいます。それをいかに正確に表現できるか、自分の気持ちにぴったりくる言葉を探せるか、じっくり悩んで書き出してみてほしいのです。
こちらは最近実際にプログラムに取り入れはじめているのですが、「子どもの時に嫌いで食べられなかったもので今は大好物なものはありますか」と質問します。セロリの匂いがいやだった、牡蠣の苦みがダメだった、フキが食べられなかった、ヨーグルトの酸っぱさがいやだった、と皆さん1つや2つはダメだったものがあるものの、大人になるにしたがっていつの間にか食べられるようになったばかりか、大好きになった、というのです。
人間の味覚の原点は甘味だと言われます。赤ちゃんの時には酸味や苦味のあるものを反射的に吐き出します。それが食べるという経験を重ねることで、味覚は広がり鍛えられていくのです。「子どもが嫌いだからといって初めから食べさせないのではなくて、一口でも味見させるようにしたら、いつかこのおいしさに目覚める時がくるかも」、ときゃらぶきをつまみながら感想を述べてくれたお母さんがいました。
一方で同じ質問に対しても、60代後半の参加者からは、「私らが子どもの頃は食料難でしたから、嫌いなんて言ってはいられませんでした。口に入るものさえあればなんでも食べましたよ」との声があがりました。ごもっとも!子どもの頃から食べること自体に不自由したことがない世代だからこそ、好き嫌いを言えるんだな、と反省するとともに、さらに贅沢な時代に育っている子どもたちのことがやはり気になった1日でした。
2004年3月 サカイ優佳子