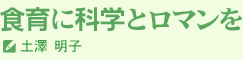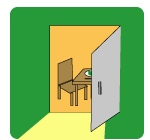「えいようし つちざわ なんだよ」。小学3年生のAさんは、給食の時間になると笑顔いっぱいにやって来て、こんな乱暴な言葉を投げかけるのです。そして私はAさんに、「質問する時に、そんな言葉を使うのはおかしいね。『栄養士、土澤さん、今日の給食は何ですか』って聞こうね。今日の献立は○○ですよ」と来る日も来る日も同じセリフを言い、それを聞いたAさんは、給食の見本をながめてから教室にもどります。
今はパターン化されていますが、最初からそうだったのではありません。始めは、「えいようし つちざわ なんだよ」の「なんだよ」の意味が理解できず、ケンカを売る「ナンダヨ!」だと思いました。しかし、Aさんの満面の笑みが挑発だとは思えず、「なんだよ」の意味を考えました。すると、「あぁ、今日の献立は『何だよ』ってことか」と思いついたのです。そして「なんだよ」の部分を「今日の給食は何ですか」に翻訳してみたのです。
子どもは、いつでもどこでも様々なメッセージを私たち大人に投げかけています。それは、食卓をはじめ「食」をとりまく場面も例外ではありません。また、投げかけている言葉やしぐさが、思いをそのまま伝える直球とも限りません。日常の中で起こる様々な出来事に動揺し、感情のコントロールが上手くつかないこともあります。また、人との距離が上手くとれずにいることもあります。そんな子どもたちが、自分のこころのメッセージを思うように投げられない時にこそ、キャッチする側は、「どこに投げてきても受け止めるつもりでいるよ」というサインを出したいものです。それは、子どものメッセージを受け止めることが出来るかどうか、上手く理解出来るかどうか、ということではないのです。むしろ、子どものメッセージを受け止めようとする人が「ただそこにいる」ということが重要なのです。
頻繁にひと口だけ飲み残した牛乳を返しに来る子ども、友達とふざけているわけでもないのに、みかんをグーの手で思いっきり叩き潰す子ども、何のためらいもなく、嫌いな食べものを床に捨てながら食べる子ども、「食」の扉を開くとこんな姿があり、様々な子どものこころが感じられます。「食」の扉の向こうには、言葉にならない思いがあふれているのです。そんなモヤモヤした気持ちを抱える子どもに、「『食』に開いた扉の向こうにどんな思いがあるのか」、「『食』の扉を通して何を伝えようとしてくれているのか」という視点を持ってかかわれば、きっと扉の向こうから言葉にならない思いを伝えてくれると思うのです。
だから、Aさんの乱暴な言葉使いを何とかして早く直そうとするよりも、来る日も来る日も同じように注意をしながら、かかわり続けることに意味があるのだと思えます。「えいようし つちざわ なんだよ」に込められたAさんの思いを知ろうとしつつ、あきるほどにかかわり続けていたら、きっといつの日か何食わぬ顔で「栄養士、土澤さん、今日の給食は何ですか」と言ってくれるのだと思っています。
土澤 明子 2005年3月