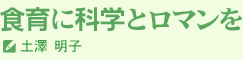小学2年生のAさんは、ひょろっとした色白で、ピンクの似合う奇麗なお嬢さんです。小食だとは聞いていましたが、そのやせ方が気になります。そこで、Aさんの食事の様子を見に行くことにしました。そーっとAさんの近くに寄って声をかけようとすると、念仏のように何かを唱え、一心不乱で食べています。耳を澄ませて聞いてみると、「○円だから食べなくちゃ、○円だから食べなくちゃ」と言っています。その時、私は、驚きと同時に、言葉にならない悲しみが湧いてきました。しかしなぜ、Aさんは、そんな言葉をつぶやきながら食べていたのでしょう。
横に屈んだ私は、Aさんに「おいしい?」と声をかけました。返事のないAさんに続けて私は「今、何て言って食べていたの?」と尋ねました。Aさんは、「○円だから食べなくちゃダメなの」と答えました。私は「ふーん、そうなんだ。よく○円って知ってるね」と言うと、Aさんは、「お母さんに『1食○円払っているんだから、残さず食べないとダメでしょ』と怒られる」と言います。そして、全部食べ切れなかったAさんの落胆した姿には、目を覆いたくなり、かける言葉も見つかりませんでした。
確かに食と経済は切り離せないものであり、「○円を無駄にしないように食べる」という考えは大切です。だから、残さず食べる理由を経済性に求めたお母さんが間違っているとは思いません。でも、「残さない方が良いのだ」と教える理由はそれだけではないはずです。おいしい料理を作ろうとする人の思いや安全で品質の良い食材を作り、売る人々の思いとの繋がり。また、何よりも、「他の生き物の命をいただいて、私たちは生きているのだ」という感謝の気持ちこそ、「残さないほうが良いのだ」と教えるには十分過ぎる理由だと思います。
大人の不用意な言葉や冗談を真剣に受け止め、一生懸命に頑張っている子どもが少なからずいます。Aさんもその一人です。難しいことかもしれませんが、食の「お金」という、目に見える側面も大事にしつつ、目には見えない「繋がり」に、感謝の気持ちをもてる言葉をかけたなら、食は豊かになると思います。
土澤 明子 2005年7月