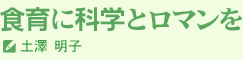「子どもたちの消化器心身症は、家庭の食卓の雰囲気と深いかかわりがある」と聞いたことがあります。消化器心身症は、心理的なストレスによって、自律神経やホルモンのバランスが崩れることなどによって起こります。検査をやっても異常はないけれど、お腹が痛かったり、胸やけがしたりするものから、消化性潰瘍や過敏性腸症候群などがあります。大人でも緊張すると、胃が痛い、下痢をする、などと聞くことがあります。しかし、心理的なストレスで消化器の症状が現れるものなのでしょうか。
コーネル大学のウォルフらによる「トムの実験」という、感情と消化器の関係を調べた研究があります。この研究は、トムという成人男性のお腹に開いた穴から、胃の中の様子を観察したものです。トムが長い間不安でイライラしていた時、彼の胃の粘膜は赤くなり、やがてただれや出血が起こったと報告されています。ということは、子どもたちも不安やイライラが続くと、トムのようになってしまうかもしれません。
「早く食べなさい!」「こぼさないの!」「残さないのよ!」などと、日々の食卓で子どもたちが言われていたら…。「ガミガミ言われるの嫌だなぁ」「また注意されるよぅ」などと思って、毎日の食卓はビクビク不安で、イライラする場になるでしょう。子どもたちが、緊張しながら不安を抱えて食卓に向かうと、食欲がなくなったり、胸やけがしたり、胃が痛かったりと、子どもたちのこころとからだに影響するかもしれません。
食べるということは、単に人間が生きるために栄養素をとりこむ行為ではなく、人間の感情交流にもなっています。子どもたちの今日1日の辛かったこと、悲しかったこと、ガマンしたこと、そういった思いは、食べながら交わされる会話や心地よい雰囲気、そしてその関係によって消化されていくのです。食べものが子どもたちのからだを育てるように、食卓でのかかわりがこころを育てます。緊張や不安よりも、笑うことの多い食卓には「こころとからだに福来たる」です。
土澤 明子 2006年1月