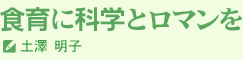節分の日、小学生の子どもをもつ友人から、こんな質問のメールが届きました。
「今日の給食は、節分の行事食で大豆とイワシだったんだけど、気がついたら週に何回も大豆を使っている。これじゃ年中節分だよ。やっぱり大豆イソフラボンがイイからかな。でも、乳がん予防って年じゃないよね」。
同じような質問を耳にすることが多いのですが、みなさんも気になっているのでしょうか。
大豆イソフラボンは、最近話題の栄養素の1つです。からだが錆びるのを防いだり、肩こりを解消したり、乳がんを予防したり、と何かとからだによさそうです。でも、大豆を給食の食材として使う理由は、何もこの大豆イソフラボンの働きを期待して、摂取量が決められているわけではありません。どうやら有名になり過ぎたイソフラボンが一人歩きしているようです。
平成15年に文部科学省は、「学校給食の児童又は生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準」を改訂しました。この改訂された「学校給食における食品の構成について」の中に、「豆類は、脂質とたんぱく質を多く含み、古くから動物性食品に代わるものとして日本人に摂取されてきたが、これまでは、豆類のなかでは、豆製品が中心に摂取されているため、植物性たんぱくの豊富な豆の摂取についても配慮すること」という留意点があります。これを受け、都道府県の教育委員会の多くが「学校給食の栄養摂取基準」を改め、標準食品構成表において豆類と豆製品を区別し、それぞれに摂取目標を示したのです。そのため大豆が多く使われるようになりました。
何だか難しい話です。簡単に言うと、以前は大豆や小豆などの「豆類」と「豆腐」や「油揚げ」の豆製品をひとくくりにし、「豆・豆製品」という枠組みに摂取目標が示されていたので、大豆や小豆などの「豆類」を「豆腐」や「油揚げ」にかえて目標量を満たすことが出来たのです。ところが、基準が新しくなり、「豆類」と「豆製品」が区別され、それぞれに目標量が示されたため、大豆や小豆などを摂取しなければ、「豆類」の目標量を満たすことが出来なくなりました。だから、大豆を使う献立が多くなったというわけです。
さて、職種の違う友人に、これだけを解説するのも何なので「大豆の摂取量が増えれば、ピクリとも動かない日本の自給率を上げられるかもね」と加えて返事をしました。
土澤 明子 2006年3月