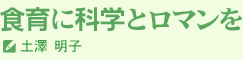動脈硬化という言葉を聞いたことがありますか。動脈硬化は病気の名前ではありません。血管の壁にコレステロールがくっついて、ドロドロとしたやわらかい塊ができ、血管の内側が狭くなったり、弾力性を失った血管がもろくなり、血液の流れが滞ったりする状態をいいます。動脈硬化がすすむと、脳梗塞や心筋梗塞などを起こしやすくなります。脳梗塞や心筋梗塞などの心血管疾患は、日本の死因でもガンに匹敵し、働き盛りに突然なることが多く、死亡したり、後遺症に悩んだりと、大きな社会問題になっています。病気になった本人も家族も会社も苦しむことが多いので、何とか予防しようといろいろな人が対策を考えてきました。
これまでは、コレステロールが高いと動脈硬化になりやすいので、コレステロールを低くすれば心血管疾患を予防できると考えていました。しかし、コレステロールが高くない人でも動脈硬化性の心血管疾患になるので、コレステロールを下げるだけでは十分予防ができませんでした。そこで、いろいろと調べていったら、動脈硬化の危険因子である高脂血症や高血圧、糖尿病は、腸を包んでいる膜と膜の間などに脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満の人に集まりやすく、動脈硬化性の心血管疾患になりやすいことがわかりました。そして、内臓脂肪の蓄積・高脂血症・高血圧・糖尿病など、動脈硬化を起こす危険因子が集まった状態を「メタボリックシンドローム」というようになりました。
診断基準は、おへその周りが男の人なら85cm以上、女の人は90cm以上で、さらに血圧・血糖・血液中の中性脂肪かHDLコレステロールのうち2つ以上が異常になると「メタボリックシンドローム」と診断されます。
今、この「メタボリックシンドローム」の診断や治療については、賛否 いろいろな意見が出てきています。しかし、診断や治療の是非はともかく、生活習慣病の予防には食生活への配慮が欠かせません。次回は「メタボリックシンドローム」と食生活についてお話します。
土澤 明子 2007年2月