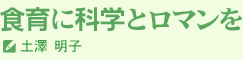「フードファディズム=food faddism」という言葉を知っていますか?アメリカで問題となったこの言葉を、日本に広めた高橋久仁子さん(群馬大学教授)は、フードファディズムを「食べものや栄養が、健康や病気に与える影響を過大に評価したり、信じたりすること」と説明しています。先頃話題となった、健康情報をねつ造したテレビ番組は、まさにフードファディズムです。
健康情報番組の特徴は、「○○で△△が治る」とか「◇◇で痩せる」など、ある特定の食べものや栄養素をとることで、魔法のごとく病気が治ったり、体重が減ったりするという情報に加え、食べものに含まれている栄養素の中のたった1つ取り上げて、「良い」「悪い」で判断していることです。
栄養相談外来には、健康情報番組に振り回されて、あふれかえった健康情報と買い込んだ健康食品やサプリメントを目の前にして、何がホントの情報で、何が自分に必要なのかわからなくなり、混乱している方も来られます。この混乱は、健康指向や健康に関する情報がホントかどうか落ち着いて考えられないくらい、世の中に健康情報が氾濫し、どの情報を信用してよいのか、わからなくなってしまっているためではないでしょうか。
からだに必要な栄養素も過剰にとれば害を及ぼします。場合によっては、毒が薬になるように、ある1つの栄養素が「良い」「悪い」などと、そう簡単に決められるものではありません。また、現在の科学を基にした栄養学では、特定の食べものや栄養素で、魔法のごとく病気が治ったり、あっという間にやせたりすることはないのです。
健康なこころとからだを育む食生活の基本は、毎食「主食+主菜+副菜」の3つのお皿を揃えて、おいしく、楽しく食べることです。健康食品やサプリメントは食事の代わりにはなりません。あくまでも、基本の食事を大切にし、それで足りなければ補うものだということをお忘れなく。
あなたも、フードファディズムの魔法にかかっていませんか。
土澤 明子 2007年8月