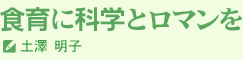梅雨入り間近のある日のことです。「梅の実って毒なの?梅雨入りしてからじゃないと採っちゃダメ?もう随分大きいけど・・・」と、Aさんが言うと、すかさずBさんが「梅毒っていうじゃない。梅干しの種を割ると天神様が出てくるでしょ。あれ、あれ、あれを食べちゃダメなのよ。神様食べると罰当たるわよ」と言いました。Bさんのあまりの説得力に、私も一瞬納得してしまいましたが、Bさんの説明はどこまで本当なのでしょう。
梅の種を割ると出てくる白い部分の「仁」(これが天神様と呼ばれているものです)や、未熟な果実の果肉中には、アミグダリンやプルナシンなどの青酸配糖体という有毒成分が含まれています。青酸配糖体自体に毒性はないのですが、果肉に含まれている酵素や胃の中の酵素と反応して青酸が生じます。この青酸中毒によって、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢などの症状が現れ、大量に摂取して症状がひどくなると、呼吸困難を起すこともあります。また、梅のアミグダリンによる致死量は成人で300個、子どもで100個程度といわれていますが、そんなに食べませんから心配いりません。といっても、わざわざ生食するのはやめておきましょう。
ところで、有毒成分はずっと含まれたままなのかというと、梅が成熟するにつれて減ってきますし、加熱調理によって減らすことができます。梅酒や梅干しにすれば1ヶ月ほどで毒性はなくなります。農林規格検査所の調査によれば、果肉や漬け込み液に毒性はほとんどないとされていますので、こちらも心配無用です。
ちなみに、梅と同じバラ科の植物の桃、杏などの種のほか、アジサイにも青酸配糖体は含まれており、6月下旬、茨城県の飲食店で料理に添えられていたアジサイの葉を食べて、吐き気などの食中毒症状を訴え、病院に搬送されたという報道がありました。これまで口にしたことのない食べものには注意しましょう。
それから、Bさんの説明の真偽のほどですが、笑いを誘う勘違いにお気づきでしょうか。「梅毒」は、植物の梅による中毒ではなく、細菌が起す性感染症の病名です。くれぐれもお間違えなく。
土澤 明子 2008年7月