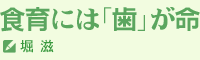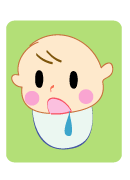唾液中には種々の物質が含まれており、それぞれ色々な作用が知られています。今回は
1 抗菌作用
2 消化吸収を助け、味覚を引き出す作用
3 中和作用〔緩衝作用〕
の代表的な3つの作用について簡単にお話させていただきましょう。
まず抗菌作用についてですが、口や鼻には、私たちの体と外界との検問所のような働きがあります。口から容易に外敵が侵入するようでは、あっという間に病気になってしまいます。唾液中には、免疫抗体やラクトフェリン、リゾチウム、といった抗菌物質が多く含まれており、私たちの体の、さまざまな防御システムの中の門番をしています。さらに唾液で口腔内を常に洗い流すことにより、口腔内の雑菌などは胃に運ばれ、胃酸により死滅することになります。また唾液中のペルオキシダーゼには、発ガン物質の毒性を減弱させる作用(活性酸素除去作用)があることもわかりました。
そして次の2番は、皆様ご存知の、食に関連した作用です。唾液中の消化酵素のアミラーゼは、デンプンを分解して、麦芽糖という私たちが吸収しやすい形の物質に変えてくれます。ご飯が、噛めば噛むほど甘くなるのがこれです。ここで皆様に憶えておいていただきたいことがあります。麦芽糖とは、ブドウ糖の分子が二つくっついた糖のことなのです。詳細は今後お話しますが、これは、甘くない食べ物でも、デンプンが含まれていれば虫歯の原因になるということを意味しています。
一方別のガスチンという酵素には味覚神経を刺激して味覚を敏感にする作用があります。しっかりマスティケートすればするほど、グングン美味しさが出てくるのです。
そして最後の中和作用、これは虫歯のメカニズムと深いかかわりがある歯科的には最も重要な作用です。この作用は唾液中に含まれるイオンや重曹によるものです。先ほどお話したように、ご飯を食べただけでもアミラーゼがデンプンを分解して、口の中に糖が出来てきます。虫歯の原因菌であるミュータンス菌はこの糖が主食です。そして、糖を食べると、その食べかすとして酸が出来てきます。そのため、お口の中は5分とたたぬうちに、全体が酸性に傾いてしまいます。いわば、歯が酸の海につかった状態になってしまうのです。この時の酸性度(ph)がある一定値よりも酸性になってしまうと、歯の表面からカルシウムが唾液中へと失われてしまいます。これが、虫歯の始まりの脱灰という現象です。しかしこの時、唾液が沢山出ると、先ほどの重曹の働きで、酸性に傾いていたものが、再び中性に戻されて歯を守ってくれます。この、歯を守る作用のことを唾液の緩衝能と言います。緩衝能の強さは人により異なりますが、歯科医院で簡単に調べることが出来ます。緩衝能の弱い人や、唾液の少ない人は酸性になっている時間が長くなるので、虫歯になりやすいことになります。しっかりとマスティケートすることが、虫歯の予防になるのはこのためです。
人体はよく地球に例えられます。重曹が体の環境を一定に保てるようにしてくれる恒常性も、もとをただせば、私たちの生命の生まれ故郷である海に、もともとそなわっている力なのです。その点をよく考えてみると、私たちが本来の健康を保つための一番の近道は、自然環境を大切にすることに尽きるではないでしょうか。自然環境を大切にすることが、すなわち自分自身を大切にすることであることを忘れないようにしましょう。
次回からは先ほど少しお話した虫歯の成り立ちや、個人個人ことなる虫歯のなりやすさの違いについてお話させていただきます。
一日に5回も6回も気をつけて磨いているのに、どうしてすぐに虫歯になってしまうの?とお悩みの方、その疑問にお答え致します。
2005年4月 堀 滋