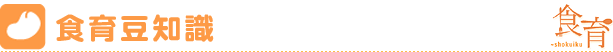私たちは、食べものからもらった様々な栄養素を消化、吸収し、代謝することで生きています。代謝とは、食べものの栄養素をからだの成分に合成したり、エネルギー源にしたりする体内での変化を言います。この生命を支える代謝には、「基礎代謝」「生活活動代謝」「食事誘導性代謝」があります。
「基礎代謝」は、私たちが生きていくうえで最低限必要な代謝で、呼吸をする、体温を維持する、胃や腸、心臓などを動かすなどの生命を維持する活動です。また、古くなった細胞を新しいものと入れかえること、骨を作りかえること、いらない物質を尿や便、汗、呼気にしてからだの外に出したり、酵素によって解毒したりすることも基礎代謝です。この基礎代謝に使われるエネルギーは、1日に消費されるエネルギーの60〜70%と考えられていますが、性別、体重などによって異なり、年齢とともに低下します。
「生活活動代謝」は、仕事や家事をしたり、運動したりして、からだを動かすことで消費されるエネルギーです。1日に消費されるエネルギーの20〜30%とされています。
「食事誘導性代謝」(または「特異動的作用」)は、1日に消費されるエネルギーの約10%とされる食べたものを消化、吸収するために使われるエネルギーのことです。食べものを噛み砕いたり、飲み込んだりする動作によって、エネルギーが消費していることを自覚するのは容易です。しかし、消化や吸収のために胃や腸が動いたり、消化酵素を出したりして内臓が大忙しで働いていることを実感するのは難しいことです。ともかくも、わたしたちのからだは意識しなくても常にエネルギーを必要としています。
ちなみに、この常に必要としているエネルギーの単位には、kcal(キロカロリー)が一般的に用いられますが、1kcalとは1kgの水の温度を14.5℃から15.5℃に、1℃上昇させるために要する熱量のことをいいます。