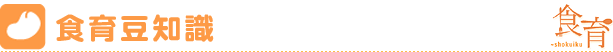生活習慣の変化とともに高齢社会となった日本では、糖尿病などの生活習慣病やその予備軍の人が増えました。と同時に医療費も増加し、国民医療費は約32兆円に膨れ上がり、その国民医療費の約3割を生活習慣病が占めています。生活習慣病に使われる10兆円という金額は、1年間に納税される消費税の額とほぼ同じです。
この増え続ける医療費を抑制するために、国は平成20年4月から「特定健診・特定保健指導」という新しい健診制度を始めました。この制度は、40歳から74歳の医療保険加入者(被扶養者を含む)を対象に行なわれます。しかし、なぜ健診という方法をとったのでしょうか。
それは、健診で異常が見つかった項目が多いほど、10年後の患者一人当たりの医療費が高くなっていたからです。たとえば、異常なしの人では約14万円でしたが、肥満や血圧、脂質、代謝系に異常のあった人では約45万円になり、約3倍も高くなっていました。
また、10年前の健診結果をたどってみると、代謝系の検査項目に異常がなくて糖尿病になった人は約7%でしたが、代謝系に異常のあった人では約43%が糖尿病患者になっていて、その差は約6倍にもなっていました。
どうやら生活習慣病によって、国の財布も痛み、患者本人の財布もからだも痛み、なおかつ病院通いに貴重な時間が奪われているようです。
生活習慣病は予防可能です。食生活の見直しや適度な運動によって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などを減らし、医療費を抑えること。これが「特定健診・特定保健指導」の目的です。
そして「特定健診・特定保健指導」は、内臓脂肪の蓄積に高血圧、高血糖、脂質異常という危険因子を2つ以上もつメタボリックシンドロームに着目して行なわれます。メタボリックシンドロームとその予備群と判定された人は、自分の生活習慣の問題点を医師、保健師、管理栄養士と一緒に改善していく「特定保健指導」を受けることになります。詳しいことは次回お話します。