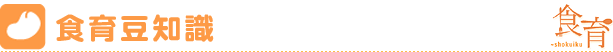新しい健診制度“特定健診・特定保健指導”が始まりました。“特定健診・特定保健指導”は、40歳から74歳の人を対象に行なわれる腹囲測定、血圧、血糖、脂質などの健診で、メタボリックシンドローム(以下メタボ)とその予備群かどうかが判定されます。該当者は、専門家による保健指導を一定の期間受けた後、これまでの生活習慣が変わったか、メタボが解消されているかなど、効果の確認が行われます。
この制度に先駆け、社員のメタボ解消に取り組む日立製作所健康管理センターの中川医師は、メタボを「あなたの血管は実年齢と比べて早くに硬く、厚く、狭くなっていきますが、本当によろしかったですか症候群」と、ユニークでとてもわかりやすく説明しています。
また“特定健診・特定保健指導”については、「実年齢と比べて血管が老けてしまうメタボの進行を止めるために行い、検査の結果で動脈硬化の危険度別に3段階に区分し、ひとりひとりに動脈硬化の危険度を知らせて、危険度が高いと判定された人は、生活習慣の見直しについて、医師、保健師、管理栄養士による“特定保健指導”という支援プログラムを受けること」と、こちらについてもわかりやすい説明がされています。では、この“特定保健指導”とは、どのようなものなのでしょうか。
“特定保健指導”は、腹囲や動脈硬化のリスクの数によって「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の3段階に分けられます。「情報提供」は健診受診者全員にパンフレットなどで情報が提供されます。「動機づけ支援」や「積極的支援」については、医師、保健師または管理栄養士が、生活習慣の改善に取り組む気になるような動機づけをしたり、行動の計画を立てたりする面接を行います。「動機づけ支援」は、その面接が原則1回行われ、「積極的支援」はさらにきめ細やかに、面接や電話、e-mailなどを使って3ヶ月以上継続して行われます。どちらも6ヵ月後に改善されているかどうか評価されます。
現在、いろいろな国が肥満対策を行っていますが、成功した国はありません。この日本の保健指導による肥満解消に世界が注目しているようです。