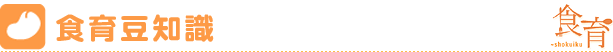「食べたい」という欲求が、いつでもどこでも限りなく起こったら…それは一大事です。だから、生き物は「食欲」という機能で食べる量をコントロールしています。食欲は、脳の視床下部という場所の摂食(空腹)中枢で生み出される「空腹感」と、飽食(満腹)中枢によって生み出される「満腹感」で調整されています。今回は、満腹感についてまとめてみます。
満腹感が生まれるしくみはいくつかあります。
1つ目は、歯ごたえ、噛みごたえの感覚が口から脳に伝えられると、神経ヒスタミンという満腹物質が増加して満腹感が発生するという考えです。減量の際に、「早食いをせず、噛む回数を増やしてゆっくり食べましょう」と言われる理由がここにあります。
2つ目は、胃が食べもので満たされると、胃は膨れて大きく広がります。この胃の拡張によって胃に分布している迷走神経が刺激され、これが脳に伝わり、視床下部で満腹感が生み出されるというものです。
これは、エネルギーが低くてもカサがあれば、胃が膨れて満腹だと感じるということです。これも減量のコツと言われています。ところが、低エネルギー食品を食べた後に「お腹はいっぱいになったけど、何か物足りない。ちょっと食べたい」と思うことがあります。それは3つ目のしくみが説明してくれます。
3つ目は、食後に血液中のブドウ糖が増えると生まれる満腹感です。食事の前に甘いものを食べると、食欲が落ち着いてしまうという経験があると思います。これは、食べものの糖類が消化、吸収され、血液中に入ったブドウ糖が脳に到達して満腹感が発生したためです。また、最近では、脂肪酸やアミノ酸などの栄養素も満腹感に影響することがわかってきました。
食事をして「お腹がいっぱいになったから、もうおしまい」と箸を置けるのは、これらのしくみによって満腹感を感じるからです。空腹の野生の動物は満腹になれば食べるのをやめます。おいしいからもっと食べよう、いつ獲物がとれるかわからないから今のうちに食べておこう、といった理由で食べません。私たち人間も動物と同じ生き物ですから、満腹感を素直に受け入れたいものです。