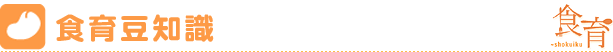「梅干の酸っぱさが健康にいいって言うから、毎食食べています。
でも、酸性食品をそんなに食べて平気ですか」
と、真剣に質問するAさん。梅干を毎食食べることの是非をお話する前に、アルカリ性食品と酸性食品について説明する必要があります。
アルカリ性食品と酸性食品の分類は、リトマス試験紙やpH計などを使って食品そのものを計るのではありません。食品を燃やして残った灰を水に溶かし、その液に含まれるミネラルのうちナトリウム、カルシウム、カリウム、マグネシウムなどのアルカリ性元素の量が、酸性元素のイオウ、リン、塩素などの量よりも多ければアルカリ性食品とされています。酸性食品はその逆です。
つまり、食品中に含まれるミネラルの量をもとに、アルカリ性食品と酸性食品は分類されているのです。だから、梅干は酸っぱいから酸性なのではなく、ミネラルの含有量からアルカリ性食品とされます。その他果物、野菜、大豆、牛乳、イモ類、海藻類などもアルカリ性食品に分類されています。一方の酸性食品と言われるものには、穀類、肉、卵、魚、大豆以外の豆などがあります。
ところが、Aさんに説明する必要があるのは、このようなアルカリ性食品、酸性食品という分類についての話ではないのです。最も強調し、きちんと説明しなければいけないことは、「以前『肉などの酸性食品ばかり食べると、弱アルカリ性に保たれている血液が酸性になってしまうので、アルカリ性食品を食べて血液をアルカリ性にしましょう』などと、アルカリ性食品の摂取を促す話がありました。しかし今では、“食べものによって血液のpHは変らない”とされていますので、アルカリ性食品、酸性食品と分けることも、アルカリ性食品はからだに良い、酸性食品はからだに悪いと分けることも、健康づくりに役立たない」ということです。
また、「梅干はおいしいけれど、1日3個も食べると塩分の摂り過ぎにつながります。種類や大きさにもよりますが、梅干1個には約2gの塩分が含まれています。1日1個というのはどうでしょう。これは健康づくりに大いに役立ちます」と、強くオススメする必要もあります。