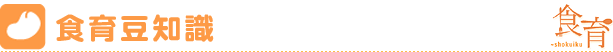「家で血圧を測りましょう」
そう医師にすすめられた父が、「どんな血圧計を買えばいいのか」と、電話をしてきました。
家庭血圧の測定は、白衣を着た医師や看護師に測ってもらった時にだけ高くなる「白衣高血圧」や、その逆の診察時は正常なのに、家庭や職場で自己測定した時は高くなる「仮面高血圧」の診断、また服薬中の降圧薬の調整に役立ちます。血圧は高ければ高いほど脳卒中や心筋梗塞になりやすく、死亡率も高くなりますから、正確な血圧を知り、診断するためにも家で血圧を測ることは大切です。
2000年の「第5次循環器疾患基礎調査」によると、日本人の30歳以上の男性47.5%、女性43.8%が、高血圧とされる収縮期血圧(最高血圧)140mmHg以上、または拡張期血圧(最低血圧)90mmHg以上、あるいは降圧薬服用中であり、高血圧者の総数は約4000万人にのぼることがわかっています。
日本人の高血圧の特徴として、食塩の摂取量が多いことがあります。現在の食塩摂取量は1日11g〜12g程度といわれています。ちなみに1950年代の東北地方の食塩摂取量推定値は1日25gですので、これに比べると現在の1日12gは随分少ないように思えてきますが、健康日本21の食塩摂取量の目標値は1日10g未満ですので、まだまだ減らすことが望まれています。
ところで、1日当たり食塩を3g減らすと、収縮期血圧が1〜4mmHg低下すると考えられています。「1〜4mmHg下がるくらいでは…」と思われるかもしれませんが、国民の収縮期血圧水準が2mmHg低下すると、脳卒中になる人が約2万人、虚血性心疾患になる人が約5000人減ると考えられています。ですから、ほんの少しの減塩でも効果が表れます。また、近年肥満を伴う男性の高血圧者が増加しており、減塩はもちろんのこと、肥満解消に努めることも必要です。
さて、父への回答ですが、「使い勝手のいい指用や手首用の血圧計は、不正確になることが多いって言われているから、上腕用がいいね。それから、測定値に一喜一憂する必要はないし、気にして日に何度も測らないでね」と伝え、父の日に自動上腕式血圧計をプレゼントしました。